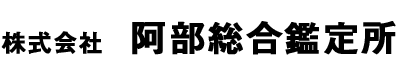ここで明治維新に大きな影響を与えた討幕派の薩摩、長州、土佐藩(藩主以下、上士は主に佐幕)そして佐幕派の会津、幕末にあだ花のごとく咲き、京都で勤王の志士たちをふるい上がらせた新選組、尊王派の水戸藩の藩風を司馬氏はどのようにとらえていたのか。
幕末の歴史を考察するうえで参考になると思うので見てみよう。
薩摩の藩風
・地理的に、西南隅にいて、しかも一藩鎖国を取っているために、戦国の士風をそのままに温存しているといっていい。
遠く思えば、秀吉、家康の二代にわたって、薩摩の島津はこれらの支配者が政権を取る時期に反抗し、しかも領土を取り上げられずに安堵されている。
兵馬の強さを恐れられたのである。
中略、
またこの国には、独特の剣法がある。
一藩これを修錬している。世間では示現流という。
薩摩では「お国流」という。
中略、
撃つところも、面、籠手、胴、というようなものではない。
左袈裟、右袈裟のひと手である。
敵に向かって全速で走りながら、左右交互に斬ってゆく。
受け太刀はない。防御というものはなく、ひとすじの攻撃である。
太刀うちはすさまじく、薩摩の示現流に斬られた死体は、惨としてひとかたまりの肉塊に化すほどにむごい。(竜⑤p179・180)
・薩摩藩というのは沈黙の巨人、といった不気味な印象がある。
なぜならばこの藩の最大の特徴は一藩統制主義で、すべて組織全体で動く。(竜⑤p258)
・斉彬は六年前急死するまで薩摩藩を近代産業国家に改造することに専念し、鹿児島城外の磯の別邸内に、「集成館」という工場をたて、旋盤や化学工業設備を置き、鉄砲火薬やガラス製品などを生産した。
それだけでなく居間にシナ三百余州の地図を貼った大屏風を立てまわし、「シナは早晩、外国勢のために崩れる。そうなれば日本は孤立する。
危機これ以上のものはない」といい、「シナが亡国になる以前に、日本は欧米の機先を制して、九州諸藩は安南、南洋諸島に進出して占領、奥州諸藩は北進し、満州、蒙古,北シナを攻略し、シナ大陸を前後から包囲して外国勢力をはじき出さねば、日本はつぶされてしまうだろう。」
(竜⑤p318・319)
・古来、薩摩藩は一種の秘密国家で、他国人を一切入れない。
江戸初期の幕威の盛んな頃でさえ、幕府の隠密でこの藩に入国できた者はまずない。
追い返されたり、関所役人にひそかに斬殺されたりした。
そのため江戸では帰らぬことを「薩摩飛脚」といったほどであった。(竜⑥p45・46)
と司馬氏は薩摩藩の組織、人間性を述べている。
長州の藩風
・竜馬が乗り込んだ長州藩とは、そもそもどういう藩か。
煩わしくとも、この小説を読んでいただくためには、このことだけは知っておかなければならない。
なぜなら、幕末、この藩は、極端な過激主義となり、政治的に暴走を重ねて、ついに歴史を明治維新まで追い上げた主導的な藩だからだ。
藩祖は戦国の雄、毛利元就である。
元就は七十五才で歿するまでの間、大小二百余回の合戦に勝ち抜き、山陽、山陰十一ヵ国の巨大な勢力を築くに至った。
元就が死んだ元亀二年といえば、徳川幕府の祖である家康がまだ三十才そこそこの少壮で、やっと三河と遠江(とおとうみ)の一部を平定したばかりの年代だ。
要するに、徳川家よりも毛利家のほうが老舗なのである。
中略、
秀吉が死に、関ヶ原の役がおこった。
毛利輝元は思わぬ成り行きから石田三成に担がれ、西軍の形式上の旗頭として大阪城に在城したが、兵は動かしていない。
ただ分家の毛利秀元の隊のみが関ケ原に出陣したが、戦闘には参加しなかった。
家康の天下が来ることを見越していたからである。
しかし戦後、家康は毛利家に対して苛酷すぎる処置をとった。
百七十万石の毛利領を大幅に削って、長門、周防二ヵ国、三十七万石とし、居城も広島城から撤せしめて、日本海岸の萩へ押し込めた。
理由は毛利家ほどの強大な大名をそのままにしておくのは徳川家の安全を脅かすものだったからだし、またその大領土を削らなければ自軍の諸侯に呉れてやる土地がなかったからでもある。
毛利氏の領地は五分の一に縮小した。
領土は削られたが、毛利家では家臣の数を整理しなかった。
三十七万石をもって膨大な家臣団を養うために、江戸初期にすでに「産業国家」に切り替えている。
つまり幕府も諸大名も米穀経済に頼っているときに、製紙,製蝋という軽工業方式にきりかえ、かつ新田を開発し、このため幕末には優に百万石の富力を持つに至った。
幕末、他藩が農業国家として窮乏に喘いでいるとき、長州藩には十分な金があった。
富で洋式軍隊に切り替え、同じく軽工業藩であった薩摩藩とともに、幕府に対抗する二大勢力になったのである。
「徳川討つべし」という反徳川感情は、尊王攘夷という姿に変わって、若い藩士のあいだで再燃した。
その火付け役は吉田松陰であった。(竜②p366・367)
・元来、長州藩には、天下に野望がある。と近藤はみていた。
毛利候は将軍になりたがり、(と近藤は憎悪を込めて信じていた)
近藤だけでなく、母藩の会津藩が上下ともそう思い込んでいるし、のちに友藩となった薩摩藩などは強烈にそう信じ込んでいる。
その証拠に、薩長同盟の密約のとき、薩摩藩の西郷隆盛は容易に腰を上げなかった。
その疑惑があったからである。(燃えよ剣、以下燃、上、p545)