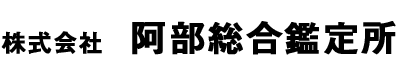ペリーの来航
江戸から明治時代に移る大きなターニングポイントとして1853年、米国のペリーが4隻の黒船で浦賀に来航したことが挙げられるだろう。
来航の理由は彼らが太平洋で捕鯨する際に食料や水、そして燃料を補給する基地が欲しかったからだ。
この時の幕府は意見がまとまらずペリーはいったん帰国。
翌、1854年、ペリーは7隻の軍艦を率いて来航。
幕府はやむを得ず日米和親条約を締結し下田と函館の2港を開くことになるのである。(その後、英、露、蘭とも同様の条約を結ぶ)
そして1858年、アメリカ総領事ハリスが日本と本格的に貿易を始めるために条約を結ぶよう強く要求。
大老、井伊直弼は朝廷に無断(勅許を得ず)で反対派の意見も抑えて日米修好通商条約を結ぶ。(函館、新潟、神奈川、兵庫、長崎の5港を開港)
この条約はその後、英、露、仏、蘭とも同じ内容で締結する。
この当時の幕府の悩みというかジレンマを司馬氏は次のようにいっている。
攘夷、すなわち勤王。
開国、すなわち佐幕。
というのが当時の図式である。
日本の国力で列強の軍を打ち払えるわけはないのだが天皇(孝明帝)はそれができると信じ、公卿もそれを信じ、かつ武市ら攘夷志士が、朝廷を焚きつけて日本政府である幕府に攘夷を朝廷から強要させている。
哀れなのは幕府だ。
「できませぬ」
とはいえず、一方では外国と条約を結んでなし崩しの「開国」をしつつ、一方では朝廷に対し「いつかはやりまする」と「対内外交」をしているのだ。
「期限はいつにする」と朝廷は脅迫同然にせまっている。
その朝廷を背後で操っているのが長州藩と土州藩武市派である。
幕府がもし攘夷が出来ぬといえば倒してしまう。
倒幕の口実にそれをする、という肚である。(竜馬がゆく、第3巻、以下「竜③」と略すp330,331)
思うにこの時期の幕府はまさに前門の虎、後門の狼的な状態でにっちもさっちもいかなくなっていたというのが正直なところだろう。
その後、日本の政権は一気に流動化していく。
安政の大獄
1858年から59年にかけて大老、井伊直弼は開国に反対する大名や学者らをことごとく処罰していく。
松下村塾を開いた吉田松陰や幕末の四賢候の一人と言われた福井藩主、松平春嶽の側近中の側近、橋本佐内もその中に含まれる。
この安政の大獄前後について司馬氏は次のように書いている。
江戸政界は開国に踏み切ったとはいえ、京都論壇は、徹底的な鎖国攘夷論だった。
到底幕府が要請する勅許を受け入れる雰囲気ではない。
当然江戸と京都は対立し、もし幕府がハリスとの約束を守ろうとすればまず京都に出没する浪人論客に大弾圧を加え、公卿に戦慄を与えねばならない。
幕末維新の血なまぐさい風雲はここから出発するのだ。
中略、
幕閣の態度が煮え切らないのでハリスは業を煮やし京都政府と直接かけあおうとした。
安政5年大老に井伊が就任し勅許を得ずに条約調印を断行するのである。
かくて尊王攘夷論が燎原の火のごとく燃え上がることになる。(竜②p34~37)
またこの大獄についてこのようにも述べている。
異変とは、世にいう安政の大獄である。
大老、井伊直弼は条約勅許問題と将軍継嗣問題について、江戸、京都で暗躍した反井伊派の逮捕を命じた。
これが安政5年(1858年)9月5日。
もっとも一斉検挙ではない。
この日を手始めとして翌、年末に至るまで公卿、大名に対しては蟄居、差し控え、隠居。それ以下の志士に対しては逮捕、江戸送りのうえ投獄,死罪、という惨憺たる事件が、この1年にわたって続くのである。(竜②p45・46)
桜田門外の変
安政の大獄に不満を抱く人が多くいた。
この大獄の2年後,1860年に江戸城桜田門を出たところで元水戸藩士(先に脱藩をして出身藩に迷惑が及ばないようにする)らが井伊直弼を暗殺してしまうのだ。
ここで司馬氏の言葉を借りよう。
竜馬が一時江戸から土佐に帰ってきて乙女姉さんの嫁ぎ先にいる時、武市半平太が旅姿で突然訪ねてくるところから始まる。
「竜馬、一大事じゃ」
「なんじゃ、お前、旅姿で」
武市は、ムチで袴をパタパタとはたき
「江戸へ発つ」
「ほう藪から棒じゃな」
「吉報があった。おそらく天下を憂える者はどよめくであろう」
「めずらしい」
「なにが」
「お前が左様に昂奮しちょるのは」
「あっは、は、これが喜ばずにおられるか」
中略、
「一大事とはなんじゃ」
「大老、井伊直弼が、江戸桜田門外で、水戸、薩摩の憂国の烈士のためにころされたぞ」
「えっ」(これは大変な世の中になるぞ)
竜馬の血が、逆流して、目のくらむ思いであった。
生涯、これほど血のわいた瞬間はない。
中略、
幕閣の首班が名もなき浪士に殺されたのだ。
これは癖になる、と竜馬は見た。
今後、俗論、軟論を持つ幕閣,諸藩の藩庁の要人はつぎつぎに殺されてゆくだろう。
「これで竜馬、草莽の正気が日の目を見たのだ。水戸、薩摩の連中は、一剣をもって天下をただした.我々土佐武士も、ぼやぼやしちょられんぞ」
中略、
江戸桜田門外で起こった井伊大老の暗殺事件は、土佐7群の田舎侍どもにも微妙な影響をもたらしている。
今まで幕府のことを「大公儀」と敬い呼んでいたのが単に「幕府」と呼び捨てるようになった。
中略、
明治維新はすでに桜田門外の変から始まったといっていいし、また、この変事がなければ維新は何年遅れたか、もしくは全く別の形のものになっていたかもしれない。
が、同じ影響でも、土佐藩の場合は、薩摩,長州の武士とは違う点があった。
土佐藩のばあい、藩公、家老、上士はなんの影響も受けず、過敏だったのは軽格である。しかもその軽格連中が、幕府を軽侮すると同様、藩そのものを軽侮し始めた。
何度も言う。
倒幕維新の運動をやった薩長土三藩は、いずれも300年前の関ヶ原の敗戦国である。
幕府には恨みがあった。が、土佐藩のばあい敗戦者は旧長曾我部家の遺臣の子孫である.軽格連中であり、藩公以下上士は、戦傷者であった。自然、佐幕主義たらざるを得ない。(竜②p218~225)
江戸幕府に300年近く虐げられてきた恨みつらみがここで一気に噴き出そうとするのである。
余談ではあるが今春、コロナ禍の中、高知に一泊旅行をし、桂浜にある坂本龍馬記念館に行ってきた。
お陰で人も少なくゆっくり時間を取って見学することができた。
ここで関が原以降、土佐に入った山内一豊とその家臣(いわゆる上士)、それ以前、土佐を治めていた長曾我部家の家臣(いわゆる郷士、下士、軽格とか言われる身分)の違いについての面白い記載があったので取り上げてみる。
・下士(軽格)は上士と行き違ったときは笠を取り慇懃を尽くし無礼無きようにする。
・上士は城下でも日笠を被ることができたが下士は5月から8月だけ被れる。
・上士は馬や駕籠に乗ることができるが下士は馬には乗れない。ただし老人や病人などが療養のため往来するのは事前に届け出し許可されればいい。
このようなことを見ても下士は土佐では武士でありながら異様な身分社会の中で虐げられていたことがよく窺える。