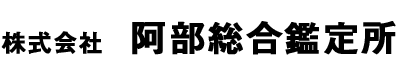【いよいよ江戸幕府の最期を迎える時が来た。1867年(慶応三年)の大政奉還である。幕府による第二次長州征伐は1866年の薩長同盟により薩摩藩は動かず(長州藩は薩摩経由でイギリスからも援助を受けていた)結果、幕府軍は長州に敗北。15代将軍、徳川慶喜は政権を天皇に返す大政奉還を行い、264年にわたってこの国を支配した江戸幕府は終結するのである】
大政奉還
それでは司馬氏の小説から大政奉還前後をみてみよう。
・(妙案はないか)竜馬は、暗い石畳の道を足駄でたたきつつ、西に向かって歩いた。
一案ある。
その案は、後藤が「頼む」と言ってきたとき、とっさにひらめいた案だが、はたして実現できるかどうか、という点で竜馬は考え続けてきている。
「大政奉還」という手だった。
将軍に、政権を放してしまえ、と持ち掛ける手である。
中略、
日本を革命の戦火から救うのはその一手しかないのである。
(竜⑦p392~394)
・海援隊文官の長岡謙吉は「ものには時機がある。この案を数ヵ月前に投ずれば世の嘲笑を買うだけだろうし、また数ヵ月後に引っ提げて出れば、もはやそこは砲煙のなかで何もかも後の祭りになる。いまだけが、この案の光る時だ。」
「左様、奇策だけに腐りやすい。ところでこの案は坂本さんの独創ですか」
「ちがうなあ」竜馬は笑いだした。
中略、
「どなたの創見です?」
「かの字とおの字さ」
勝海舟と大久保一翁であった。どちらも幕臣であったという点がおもしろい。
勝、大久保という天才的な頭脳は文久年間から、徳川幕府も長くはないと見通していた。幕府機構ではもはや天下の運営ができないことを、実地の幕府官僚であるだけに全身で感じていた。(竜⑦p405~406)
・もともと竜馬の大政奉還案というのは、一種の魔術性を持っていた。
討幕派にも佐幕派にも都合よく理解されることができる。
たとえば後藤象二郎が理解したのは、「徳川家のためにもなり天朝の御為にもなる」という矛盾統一の案、ということだった。
この点、勤王か佐幕かの矛盾に悩む山内容堂にとってはこれほどありがたい案はない。
一方、中岡のような統幕急進派にとっても、大政奉還の気球を上げることによって、合法的に討幕兵力を京に集中できるのである。
要するに、政治が持つ魔術性をこれほど見事に帯びている案はないであろう。
中略、
それに中岡が昂奮したのは、この案の提議によって土佐が一躍時勢の主流に躍り出るというということであった。(竜⑧p28)
・竜馬が岩倉邸を訪ねたのは、慶喜が二条城で奉還を宣言した翌日である。その翌十五日、慶喜は参内し、その旨を正式に奏上した。朝廷ではこれを受理した。このため大政奉還の成立は、慶応三年十月十五日ということになる。(竜⑧p352)
・諸藩は、ゆくべき道にまよっている。
「大政奉還後は」と、継之助はいった。
三百諸侯は徳川家との関係がなくなった、と継之助はいう。
継之助の解釈である。
徳川家は盟主であった。
諸大名は徳川家に対し臣従の盟をむすび、その統御に服するかたちをとってきたのが封建制度というものであり、それが徳川家の政権というものであった。
つまり、「大政」とは「大名統御権」というものであろう。
それを慶喜は朝廷に返上した。
このため徳川家はその直参だけが家来になった。
諸大名は、野に放りだされた。
「道理でいえば」と、継之助は言う。
慶喜が勝手に大名を放り出したわけであり、大名としてはあとは誰に仕えようと、自由意思にまかされてしまっている。
すぐ西に走って朝廷の大名にならねばならぬという道理はない。
自立してもいい。
「そのほかの道はない」という。
朝廷に仕えるか、自立するか、ふたつしかない、という。
徳川氏みずからが主人(盟主)たることをやめてしまった以上、徳川氏の傘下には入れないのである。
「いずれにせよ、天下はどうなるか」乱れるであろう。と継之助は言った。
(峠、中、p554,555)
【幕末、新選組は隊士の数が減ってきたので隊士の募集を行うため、土方歳三は江戸へ出向く。再び京に帰ったところ大政奉還は既におきていた。動揺している局中を、近藤は今後どのように隊を運営していくか迷っている。そんな中、土方は近藤にこれからの新選組のあり方を話す】
・「近藤さん」
と、そのあと、近藤の屋敷でいった。ほかの隊の者はいない。
「われわれは、節義、ということだけでいこう。時勢とか、天朝とか、薩長土がどうの、公卿の岩倉がどうの、というようなことをいいだすと、話が妙になる。近藤さん、あんたの体から、あかをこそげ落としてくれ」
「あか?」
「政治ということさ。あんたは京都に来てからそいつの面白さを知った。政治とは、日々動くものだ。そんなものにいちいち浮かれていては、新選組はこの先、何度色変えしなければならぬかわからない。男には節度がある。これは、古今不易のものだ-・・・・俺たちは」
歳三は、冷えたお茶を飲み干してから、
「はじめ京に来た時には、幕府、天朝などという頭はなかった。ただ攘夷の先駆けになる、ということだけであった。ところが行きがかり上、会津藩、幕府と縁がふかくなった。知らず知らずのうちにその側へ寄って行ったことであったが、かといっていまとなってこいつを捨てちゃ、男が廃る。
中略、
新選組はこの際、節義の集団ということにしたい。たとえ御家門、御親藩、譜代大名、旗本八万期が徳川家に背を向けようと弓を引こうと、新選組は裏切らぬ。最後の一人になっても裏切らぬ」(燃、下、p79・80)
【人生に繰り返しがないように歴史にも繰り返しはない。
しかし一人、一人の人生は途絶えても歴史は人の営みの中で連綿と続いていく。
幕末に坂本龍馬がいなかったら、勝海舟、西郷隆盛がいなかったら「薩長同盟」や「江戸城の無血開城」はなかったかもしれない?
歴史や人生にタラ、レバ、は禁物であるが、客観的な事実に基づいて素直に、歴史や,自身の人生を振り返ってみるということはおもしろい。
歴史も人生も振り返ってみるとその中にいくつかの大きなターニングポイントがあるものだ。
歴史は繰り返すともいわれる。
過去の歴史を客観的に学び次なる歴史を考えるということは人類にとっても大切なことだしし興味深いことでもある。
司馬遼太郎は1923年(大正12年)大阪で生れ、本名を福田定一という。
筆名の由来は「史記」の執筆者、司馬遷。
その司馬遷に遼(はるか)に及ばないという意味でつけたということである。
太郎は日本名、故につけたらしい。
明治維新は司馬が生まれる僅か、50~60年前の出来事である。
司馬の執筆時には当時活躍した人物の子や孫もたくさん生きていた。
その人たちから生の取材も出来ただろう。
各種史実に基づく文書類も豊富に残っていたに違いない。
司馬自身の創作もかなりあると思うが小説の重要な部分は史実に基づいたものと窺える。
司馬氏の幕末史に対する思いを、以上の抽出した文章の中で感じ取っていただけただろうか。】