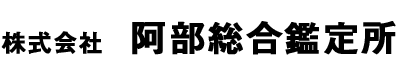これまで薩、長、土、と会津、水戸の各藩風、そして新選組の組織としての在り様などをみてきた。
ここでまた再び幕末、明治維新までの歴史的経緯とそれに関する司馬氏の思いを綴っていこう。
生麦事件と薩英戦争
1862年、尊王攘夷派の薩摩藩藩主、島津久光が江戸からの帰り道、横浜の生麦というところで薩摩藩士から見るとイギリス人の無礼な振る舞い(大名行列の際、馬から降りなかったとか、馬に乗って横切ったとかいわれている)に遭遇し薩摩藩士はイギリス人を殺傷したのである。
その後、イギリスは復讐として鹿児島湾に艦隊を派遣し、湾から市街地を砲撃、薩摩と戦争状態になる。
結果、薩摩はイギリスと戦争をしても到底歯が立たないということが分かり、賠償金を払って終結したのである。
この時に、薩摩は「攘夷は無理」と理解し倒幕へと方向転換したのだろう。
下関事件
同じく長州藩も攘夷に熱心で倒幕派でもあった。
1863年、長州藩は下関に砲台を設置して海峡を通過する外国船を単独で攻撃開始するが、アメリカ、イギリス、オランダ、フランスの四か国連合艦隊にコテンパンにやられる。
そこで長州藩は外国船の受け入れ、砲台の撤去を条件に和睦。
長州藩もこれで「攘夷は無理」と理解し倒幕に邁進していくのである。
その後、薩長は倒幕のための資金力、技術力や戦艦、銃砲などの武器弾薬をイギリスに依存する。(イギリスはこの時点で幕府は早晩倒れ、薩長が天皇のもとに新たな政府を樹立すると踏んでいたのかもしれない。因みに幕府方のスポンサーはフランスであった)
もともとこの両藩は幕府に対して恨みこそあれ義理も遠慮もない。
尊王攘夷から尊王倒幕へと大きく舵を切ったということになる。
薩長同盟
日本の新しい時代を切り開くには、仲の悪かった薩長が一緒になって倒幕するしか方法がない。
ここで薩摩の西郷隆盛、長州の桂小五郎などと交流、人脈のある坂本龍馬が薩長両藩の仲介役となり、これまでの対立、反目を解消し倒幕のための提携を結ぶのである。
この同盟が不発に終わっていれば長州藩は幕府長征軍に討ちとられ{一回目は長州が痛めつけられるのだが、同盟成立後の第二次長州征伐(1866年6月~8月)では、薩摩軍は出陣しなかった為、長州は幕府軍に勝つのである}維新を迎えることはなかったのだろう。
この薩長同盟に関する司馬氏の視点をみてみよう。
・正月十日、桂ら一行が無事京に潜入するとすぐ相国寺門前の薩摩藩邸に入った。
ここは錦小路の藩邸が手狭なために新たに作られたもので、前に御所があり、周りには寺や公卿屋敷などが多く、日中でも門前の人通りは少ない。
密偵の警戒にはうってつけの場所なのである。
桂らはその、奥座敷で薩摩藩の指導者、西郷吉之助と会った。
中略、
・桂は「我々は薩摩をうらんでいる」と陰湿な声で言った。
中略、
・「我々は、文久以来、一にも二にも朝廷に対し奉って勤王の大義を陳べようとした。しかしそれがかえって誤解され、天下に野心あり、などという途方もない誤解を生じ、ついには朝敵の汚名を蒙った。いまもこうむりつつある。」
われわれを陥れたのは、たれの策謀か、薩州の策謀ではないか,と言わんばかりの皮肉を込めて、桂は語った。
西郷は終始黙って桂のいうところを聞いていたが、やがて桂がひとしゃべり終わると、居ずまいをただし、その場に両手をつき、「いかにも、ごもっともでごわす」と、頭を深々と下げた。
・このことについて、桂に随行していた長州の品川弥二郎は、維新後、こう語っている。
「桂の言い分と態度は、そばで聞いていた我々長州人でさえ非の打ち所があると思った。薩州側に立って言い分を作るつもりなら、幾らも反駁できたに違いない。しかるに、「まことにごもっとも、」と一言発しただけで頭を下げていた西郷は、さすがに大人物と言わざるを得ない」(竜⑥p231~232)
(しかしこの会談は、竜馬がせっかく仲介の労を取ったにもかかわらず同盟話はどちらからも触れずじまいで終わるのである。)
・(この話を聞き竜馬は桂に)
「薩摩が口火を切らぬというなら、なぜ長州から口火を切らぬ」
「それはできぬ」桂は低くいった。
目に悲憤の色がある。
「坂本君、両藩の立場を考えてもらおう。まず薩州をみよ」桂は、薩州の立場を、こういう表現でいった。
「薩州は公然天子に朝し、薩州は公然幕府に会し、薩州は公然諸侯と交わる」要するに、薩州は同じ勤王派でありながらその遊泳がうまかった為に白昼堂々と天下の公藩として天下の政事に参加し、朝廷にも幕府にも立場がいい、という意味である。
・一転、長州はどうか。
「天下に孤立している。朝敵の汚名を着、幕府の追討を受け、白昼、路上を歩くこともできぬばかりか、藩の四境には幕軍が迫っている。
この立場にある長州の側から、同盟の口火が切れると思うか。口火を切れば、もはや対等の同盟にあらず、おのずから乞食のごとく薩州に援助を哀願するようなものではないか」「出来ぬ、」と桂は言った。
中略、
・竜馬はいった。「薩長の連合に身を挺しておるのは、たかが薩摩藩や長州藩のためでないぞ。君にせよ西郷にせよ、所詮は日本人にあらず、長州人・薩摩人なのか」
この時期の西郷と桂の本質を背骨まで突き刺した言葉といていい。
中略、
・桂はちらりと竜馬を見、すぐに視線を火鉢の中におとして、「薩州は皇家のおそばにあって尽くしている。長州は文久以来、孤軍、藩の滅亡をかけてつくしてきた。もはや、藩の命脈は幾ばくも無い。しかし薩州が生き残って奮闘してくれる以上、天下のためには幸いである。われわれは今、交渉を打ち切って郷国に帰り、幕府の大軍を討つことになるが、ほろぶとも悔いはない」この桂の言葉は、記録文章では、「薩州、皇家に尽くすあらば、長州滅するといえどもまた、天下の幸いなり」という名文になっている。
中略、
・この時の竜馬の態度を、桂側の記録文章を借りて書くと、竜馬、黙然たること稍久しく、桂の決意牢固として容易に動かすべからざるを察知し、また敢えてこれを責めず、とある。
(竜馬はこの後、夜半ではあったが薩摩屋敷に駆け付け西郷を起こし桂の言葉を伝えるのである)
中略、
・「いま桂を旅館に待たせてある。さすればすぐにこれへ呼び薩長連合の締盟を遂げていただこう」竜馬はそれだけをいい、あとは射るように西郷を見つめた。
・筆者はこのくだりのことを、大げさでなく数年考え続けてきた。
実のところ、竜馬という若者を書こうと思い立ったのは、このくだりに関係があるといっていい。
この当時の薩長連合というのは、竜馬の独創的発想ではなく、すでに薩長以外の志士たちのあいだで常識になっていた。
薩摩と長州が手を握れば幕府は倒れる、というのは、たれしもが思った着想である。
公卿の岩倉具視も思ったし、筑前藩庁に斬殺された同藩の志士、月形洗蔵もそう思い続けてきたし、竜馬と同郷の中岡慎太郎などは、もっとそれを思った。
去年の暮、中岡慎太郎が太宰府の旅寓から国元の同志に書き送った長文の論文があり非常な卓説として評価されている。
そのなかに、「自今以後、天下を興さん者はかならず薩長両藩なるべし」とあり続いて「吾思うに天下近日のうちに二藩の命に従うこと鏡の掛けて見るがごとし。而して他日、国体を立て外夷の軽侮を断つも、亦この二藩にもとづくなるべし」といっている。
すでに公論である。
中略、
竜馬は西郷に「長州が可哀そうではないか」と叫ぶように言った。
中略、
西郷はにわかに膝をただし、「君のいうとおりであった」と言い、大久保一蔵に目を走らせ「薩長連合のことは当藩より長州藩に申し入れよう」といった。(竜⑥p235~247)
(1866年1月、同盟が決まった瞬間を司馬氏は以上のように記述している)